私の不眠の原因は、発達障害の薬の副作用でしたが、身の回りには看護師で不眠に悩まされているヒト、結構います。
交代制勤務で「短時間でも寝ないといけない」というプレッシャーの中、日勤業務の慌ただしさに興奮した脳を強引にシャットダウンさせるために、睡眠薬を内服して働く人もかなりいます。

そこまでして働かないといけないのか、と戦慄した記憶が。。。
というわけで、今回は看護師の不眠問題に個人的な意見を投げつけていきたいと思います。
看護師が知っておくべき「不眠」の最新情報
不眠に関するニュースや不眠対策に関する情報をまとめていきます。
看護師の不眠に関する新着ニュース
不眠のパターンと熟睡障害の解明
- 朝に「ぐっすりと眠った」感覚が得られない場合、これを「熟睡障害」と称する。
- 熟睡障害の原因には、眠りの浅さ、中途覚醒、ストレス、うつ病、夜間頻尿、飲酒の影響などが考えられる。
- 短期間の不眠は問題とならないが、長期に渡る場合は日中のだるさや眠気、気分の悪さといった症状が生じる可能性がある。
睡眠時無呼吸症候群について
- 「睡眠時無呼吸症候群」とは、睡眠中に一時的に気道が塞がり、呼吸が止まる症状を指す。
- この症状に関連して、いびきの問題も考えられる。
- いびきがうるさいと指摘される人、もしくはいつもいびきをかく人は、この症状の可能性が高まる。
注意喚起
- 熟睡障害が長期間続くと、後に重大な健康問題へと繋がる可能性がある。
- 症状が続く場合は、医師の診断や相談が強く推奨される。
看護師には不眠が多い
まずは、看護師の不眠問題に関する情報を列挙していきます。
交代制勤務は睡眠障害
交代勤務者の8割に睡眠障害があり、6〜20年の勤続年数があると3割程度にうつ病がみられます。
また、日本看護協会のHPにも、交代制勤務の禁忌事項がまとめられており、「うつ病の既往」が相対的な禁忌事項として挙げられています。
当たり前ですが、うつ病患者にとって「休める時に休めない」環境はかなり厳しい。

一方でうつ病患者はクソほど真面目ですから、一度働き始めたら「つらい」とか訴えることができないんですよね。。。
交代制勤務と鬱病の関係
一応、補足で説明しておくと、不眠を主訴に持つ患者の20%以上がうつ病と診断されており、うつ病患者の90%以上は不眠症状と闘っています。そして、不眠は自殺と密接的な関係にあり、疫学的にも不眠症状によって自殺リスクは2倍近く上昇すると考えられています。
https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/web/15/403964/020200031/?P=2
抑うつ気分から不眠になるのか、セロトニンなどの神経伝達物質が悪影響を及ぼしているかは定かではないものの、抑うつなどの気分障害は高い自殺率をほこるため注意が必要です。

看護師は責任感が強く、ある意味で行動力も高いので、えいっ、と自殺を完遂するパターンも多いと聞きます。(看護師の人口が多いというのもありますが)

変な話、私のようなチャランポランだとつらければえいっと仕事を辞めちゃいますが、仕事に埋没するほど思考が「仕事」に占有されてしまい、解決策が「自殺」になってしまうんですよね。。。
不眠と労災
ちなみに、不眠で労災認定されるか調べたところ、精神障害であっても労災認定要件を満たせば認められます。
睡眠状況を調べるために
客観的に睡眠状況を調べるための検査などもあります。
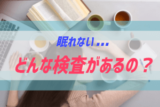
つらくて辞める仕事なら受診してもいい
仕事を退職することを考えていたら、一度、根本的な原因を見つめ直し、精神障害の可能性があれば受診しておくことをお勧めします。
- 認定基準の対象となる精神障害を発症していること
- 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6ヶ月の間に業務による強い心理的負荷が認められることお
- 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
不眠症で労災は認定されるのか
ややこしいところだけかいつまんで説明すると、今回の不眠の場合は、不眠症単体での認定は難しいと考えられます。
しかし、高確率で不眠症状は感情障害(鬱病)を併発している可能性があります。精神科医も誤診とならないように検査しますが、仕事に影響するような不眠状態は重大な精神疾患が潜んでいる可能性も高く、何にせよ精神科・心療内科の受診案件となります。
心理的負荷とは
心理的負荷を客観的に評価することは難しいですが、ある程度の基準は定められています。もっとも客観的に負荷を判断しやすいのは「長時間労働」です。看護師の場合は勤務体制の時点で心理的負荷の高い勤務とされているので、この点は簡単に認められると思います。
業務以外の要因
精神疾患は、遺伝や環境の関連も否定できないものです。因果関係を紐解くことは困難ですが、業務外に「家族問題」や「精神疾患を持つ身内」が多い場合には業務以外の誘引が強く疑われるため、労災認定とならない可能性があります。
不眠によって引き起こされる病気
脳・心血管疾患のリスク
睡眠不足でもっともわかりやすいリスクは、循環器系の疾患ですね。6時間未満の睡眠は高血圧リスクが2倍以上高く、狭心症や心筋梗塞の有病率が上昇します。4時間にかでは冠動脈性疾患による死亡率が、健康的な睡眠をとっている人の約2倍になると厚生労働白書に記されています。
ホルモンバランスの異常
ついでに、ホルモン系のバランスも崩れるとされています。
糖尿病リスク
インスリン分泌量自体の変化はないとされていますが、不規則な食習慣隣血糖値の上昇度が激しく高まるとされています。睡眠障害も関連しており、交感神経系が緊張することで、インスリン抵抗性が高まるとされています。
成長ホルモンの分泌が低下
成長ホルモンは下垂体から分泌されるホルモンですが、睡眠が不足することで分泌量が減り、肌艶が悪くなり体の回復が遅れるなどの影響があると考えられています。
免疫力の低下
あげたらキリがないな、と思い始めたところですが、睡眠が不足すると免疫系も弱ります。加えて、免疫系が働くことで体は眠たくなるようにできているのですが、無理な勤務を続けることで風邪の治りも悪くなるという悪循環を引き起こします。

30歳超えたあたりから、夜勤で風邪ひくと2週間くらい引きずってたよね。。。
ナルコレプシー
ナルコレプシーは、日中に異様に眠くなる疾患です。原因は諸説ありますが、別記事にも少しまとめてあったのでそちらを参考にしてみてください。
看護師の不眠対策
不眠対策という名の、看護師が眠れなくなることに対するメモ的なもの。
交代勤務睡眠障害
先ほど、交代勤務がヤベェという話をしましたが、「交代勤務睡眠障害」というものが存在します。
交代勤務のために睡眠時間帯が頻繁に変化することにより、睡眠をはじめ精神・身体機能の障害がもたらされる症状。
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/heart/yk-017.html
どんな治療があるの?
基本的には、睡眠時間を調整していくことで本来の生体リズムに戻していくのですが、治療として「高照度光照射」などを行う場合もあります。
昼夜逆転には短期的に睡眠薬を用いる
超短時間か短時間作用の睡眠薬を使用することで、「短時間でも入眠しやすく」します。夜勤明けなどに眠れずに昼夜逆転が改善しない場合などに使用します。ただ、短時間作用の睡眠薬は依存形成しやすいので注意が必要です。

ロゼレムなどのメラトニン作用型の睡眠薬
朝方4~5時までに眠れず、逆に昼ごろまで起きられずに完全に昼夜逆転した「概日リズム睡眠障害」の患者に処方、服用を続けてもらったところ、次第に夜になると眠くなるようになり、症状が改善された。
https://style.nikkei.com/article/DGXDZO18037070R11C10A1EL1P01/
昼夜逆転型(リズム睡眠障害)の場合は、ロゼレムのようなメラトニン作用型の睡眠薬が効果があるとされています。
ストレスから来る不眠
ストレス、というと直接的な出来事がないと想像しづらいと思いますが、看護業務はほぼストレスの塊なので「常に晒されている」として話を進めていきます。
夜勤後に襲ってくる「あれ、やったっけな」
ただのアルアルですが、夜勤が終わってようやく寝床に入ると、ふとやり残した業務を思い出すことが多いです。
元気な時は基本的に笑い話にできますが、これ、すでに脳がストレスに占有されている状況だからこそ起きる症状です。本当は仕事は仕事、プライベートに入ったら思い出さないに越したことはないのですが、心配症というかメンタル弱めな人ほど、仕事を私生活に引きずり込みがちです。
夜勤前の昼寝について
夜勤前の昼寝を上手に取ることで、多少すっきりとした気持ちで仕事に臨むことができます。また、夜勤後の疲労感にも影響があるとされています。
7時以前に起床した者、つまり夜勤当日も普段と起床時刻が変わらない者は、夜勤後の疲労感が軽減できることが示唆された。
夜勤前日の睡眠パターンが普段の睡眠パターンと変わらないこと、夜勤当日の日中に仮眠をとることは、夜勤後の疲労感の軽減につながると考えられる。
昼寝時間は3時間
仮眠の時間は15分から30分、なんてのはビジネスタイムのお昼寝の話。我々はそんなアマちょろい仮眠だとぶっ倒れてしまうので、本格的な昼寝を、どのように取るのかってのはとても重要。
勤務まえの3時間を超える仮眠により勤務後の疲労感が低下していることを示唆
睡眠サイクル
これは人によるところもあるのですが、一般的に眠りの波は90分間隔とされています。
この深い睡眠を挟むように「眠りに入るまでの時間」と「レム睡眠に入る時間」を考えると、仮眠時間を考えると、ベストは2時間の仮眠とされています。
寝溜めなんて存在しない
夜勤前に昼寝をしますが、夜勤前のに3時間仮眠するのと夜勤中に1時間仮眠を取るのは同じレベルの疲労抑制スコアということです。
不眠にならないために
看護師だからこそ毎日の生活リズムを整える
- 太陽光を浴びる
- 夜勤入り、夜勤明けに左右されずに決まった時間に寝る
- 長時間の「寝溜め」はしない
- 昼寝は3時間がベスト
- 朝食は必ず取る
- 21時ごろから眠る準備を
- 運動を取り入れる(無理)
- 脱アルコール
サーカディアンリズムをつかめ
サーカディアンリズムについてはこちらの記事をどうぞ。

体温は適度に下げる
深部体温なので直接的に冷やせばいい、というものではありませんが、体があったかいと眠りにくいという経験はあると思います。
精神科看護師としては、特に興奮の著しい患者のケアの場合には、夜間の睡眠をいかに設定するかが大切になります。その際に、部屋の温度調整は重要だったりします。これはまたいつか詳しく解説しますね。
夜勤前と後の眠り方
ベストは3時間とされていますが、子育て、家事も両立させないといけない、「できればちょっとは遊びたい」という方はここの睡眠時間を削りがち。それでも意識して1時間程度の長めの仮眠をとるように心がけましょう。
夜勤明けはとにかく午前中は寝る
私の悪いところは、夜勤明けは昼ごはん食べに行って、うだうだゲームなんかして昼過ぎから夕方まで眠ってしまっていたところ。夕方に差し掛かってしまうと、今度は夜眠れなくなってしまうので、部屋を暗くして午前中に3時間程度の睡眠を取れればだいぶスッキリします。
部屋を暗くするグッズ
しっかりとした睡眠には「部屋を暗くする」ことが大事です。
基本の遮光カーテン
当たり前ですが、部屋は遮光カーテンに覆われていると日光の遮断率がよく、快適な睡眠をサポートしてくれます。
アイマスク
部屋の対策が面倒な場合は、アイマスクを装着することで視界に入る光量を抑えることはできます。ただし、眼球周囲の圧迫感はあるので、慣れないうちは眠れないですし、朝、起きるために必要な自然採光が取れないのは問題とも言えます。
食生活を整える
食事のタイミングは大事
概日リズムを整えるためには、食事のタイミングも重要です。3食規則正しく食べるのが基本。

看護師には3食同じ時間に食べるのはしんどいし、夜勤中に何も食べるな、というのも酷な話。
グリシン
非必須アミノ酸である「グリシン」も睡眠の質を良くする栄養素だと言われています。
就寝前の体温低下を促進
魚介類に多く含まれる
眠気を妨げる悪習慣
- 寝る前のタバコ
- 多すぎる晩酌
- スマホを眺める
- 消化の悪いものを食べる

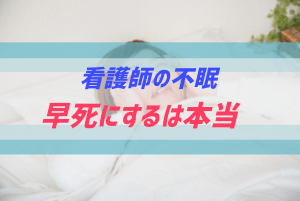


コメント
「糖尿病 ルール 改善」に関する最新情報です。
この記事では、糖尿病の改善に関する新たな「世界標準」が紹介されています。日本では糖尿病患者が増加しており、2024年には1080万人に達すると予測されています。特に高齢者が多い一方で、30代や40代の「予備軍」も約1000万人存在し、発症までの10年から15年を自覚症状なく過ごしていることが問題視されています。
糖尿病には主に「2型糖尿病」があり、生活習慣の乱れが原因とされています。著書『世界中の研究結果を調べてわかった!糖尿病改善の最新ルール』では、特に自覚症状のない「予備軍」に対して注意を促しています。35年後に発症する確率は「3人に1人」とされ、忙しい生活の中での不規則な食事や運動不足が影響しています。
血液検査で「HbA1c」が「6.0~6.4%」、または「空腹時血糖値」が「110~125mg/dL」であれば、糖尿病の境界型に該当する可能性が高いとされています。しかし、医師が診断するには限界があり、患者への指導が不十分な場合が多いことも指摘されています。糖尿病の予防と改善には、早期の血液検査や生活習慣の見直しが重要です。
https://gendai.media/articles/-/163390
「ごはん スープ スープ ごはん」に関する最新情報です。
株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、2月3日(火)から新商品「コクと旨味のキムチチゲ スープごはん」と「あったかスープの豆乳担々ごはん」を発売します。これらの新商品は、冷え込む季節にぴったりで、心とお腹を満たすことを目的としています。キムチチゲはコク深い味わいで、豚肉や野菜の旨味が溶け込んでおり、豆乳担々ごはんはまろやかな豆乳スープとごまの香ばしさが特徴です。どちらもヘルシーさを意識しつつ、満足感のある味わいに仕上げられています。価格は各430円(税込464.40円)で、全国で販売されますが沖縄県は除きます。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000678.000155396.html
「うつ病 要因 遺伝」に関する最新情報です。
この記事では、小児精神科医の内田舞氏が、子どもがうつ病になる可能性について解説しています。親が子どもにうつ病の遺伝要因がある場合、脳に特有の特徴が現れることがありますが、遺伝要因があっても脳は変えることができると述べています。内田氏は、うつ病に対する社会的偏見が根強く、親がどのように対処すべきか悩むことは自然なことだと指摘しています。彼女は、子どものうつ病や双極症の早期発見と治療の重要性を強調し、脳科学の観点からの理解を深めることが必要であるとしています。記事は、子どもの心の健康に関する情報を提供し、親や家族が直面する課題について考察しています。
https://gendai.media/articles/-/163163
「リスク リスク 上昇 上昇」に関する最新情報です。
新たな研究によると、体内時計の乱れが認知症リスクの上昇に関連していることが示されました。テキサス大学サウスウェスタン医療センターのWendy Wang氏らの研究では、概日リズムの相対振幅が低下し、リズムの断片化が進むことが認知症の初期兆候である可能性があるとされています。この研究の詳細は、2026年1月に「Neurology」に掲載されました。
https://www.carenet.com/news/general/hdn/62150
「医療 フェロトーシス 糖尿病」に関する最新情報です。
大阪大学の研究チームは、糖尿病腎における急性腎障害(AKI)の脆弱性のメカニズムを解明し、フェロトーシスがその要因であることを示しました。研究では、糖尿病性腎症の患者から得た腎生検検体やマウスモデルを用いて、オートファジー不全やAMPKの不活化、過酸化脂質の蓄積が確認されました。これらの結果は、糖尿病患者がAKIに対して脆弱である理由を理解する手助けとなり、オートファジーやAMPKを活性化する新たな治療法の開発に期待が寄せられています。研究成果は「Diabetologia」に掲載されています。
https://www.qlifepro.com/news/20260123/diabetic-kidney-disease.html
「飼い主 あったかい プチプチ」に関する最新情報です。
愛猫のきなこちゃんがプチプチに包まれて飼い主を見上げる姿が話題になっています。飼い主がSNSに投稿した写真には、「自ら梱包されに行ったんですね」「あったかいんだと思う」といったコメントが寄せられ、きなこちゃんの愛らしい仕草が多くの人々の心をつかみました。この行動はきなこちゃんの“マイブーム”であり、遊びの最中に見られることが多いとのことです。飼い主は、きなこちゃんが遊んでほしかったのかもしれないと語っています。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_69688311e4b0774cc19f037c
「明け メール 演奏会」に関する最新情報です。
このWebサイトは、日本赤十字九州国際看護大学の吹奏楽部による演奏会のクラウドファンディングプロジェクトに関する情報を提供しています。プロジェクトの目標金額は1,500,000円で、156人の支援者が参加しています。演奏会は2025年3月21日に予定されており、支援者には感謝のメールが送られ、演奏会の様子を収めた限定動画のURLが提供されます。また、支援者の店舗や個人のPRを演奏会のプログラムに掲載するオプションも用意されています。広告掲載を希望する場合は、1月13日までに連絡する必要があります。全体として、演奏会に向けての意気込みと支援の呼びかけが強調されています。
https://readyfor.jp/projects/jrckicn_brass/announcements/411351
「コツメカワウソ コツメカワウソ 昼寝 昼寝」に関する最新情報です。
山口県周南市の徳山動物園が公開したコツメカワウソのお昼寝動画が話題になっています。動画では、眠そうにうとうとするコツメカワウソたちが映し出されており、特に真ん中で爆睡している姿が印象的です。視聴者からは「寝入る寸前の表情がかわいい」「ずっと観ていたい」といった親近感を覚えるコメントが寄せられています。この動画は、見る人に癒しを与える内容となっています。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6954860de4b0c62e3c4e77c2
「未来 cycle cycle サイクル」に関する最新情報です。
東京青年会議所と株式会社まち未来製作所は、再生可能エネルギーを活用した新しい地域貢献型電力供給モデル「e.CYCLE(いいサイクル)」の推進に向けて連携協定を締結しました。この取り組みでは、電気代の一部を子どもの未来への投資に活用し、地域、企業、家庭が一体となって持続可能な社会を築くことを目指しています。まち未来製作所は、地域再生を目的とした再エネの地産地消を促進するプラットフォームを提供しており、今回の協定を通じて全国的な展開を図る意向を示しています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000052.000057319.html
「カーテン 称賛 手編み」に関する最新情報です。
「母の手編みのカーテン」がSNSで話題になり、多くの称賛の声が寄せられています。投稿者の編みちゃんさんが母の手によって編まれたカーテンの写真を共有したところ、規則正しい模様がまるで機械で編まれたかのようだと評価されました。カーテンは春から夏にかけて少しずつ完成されたもので、編みちゃんさん自身も母の影響でかぎ針編みを始めたと語っています。投稿には1.1万の「いいね」が付き、「素敵」「うまい」といったコメントが多数寄せられています。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6943a63ce4b045d9788d00c7
「高血圧 パターン 高血圧 パターン」に関する最新情報です。
Apple Watchは本日より、日本で高血圧パターンの通知機能を導入しました。この機能は、血圧が高い状態が続くパターンを検出し、ユーザーに通知します。高血圧は心臓発作や脳卒中、腎臓疾患などのリスク因子であり、全世界で約13億人の成人に影響を及ぼしています。多くの人が無症状であるため、定期的な医師の診察を受けていないことが多く、診断されないケースもあります。Apple Watchは光学式心拍センサーのデータを分析し、30日間のデータをもとに高血圧パターンを検出します。通知を受けた場合は、医師に相談することが推奨されています。
https://www.apple.com/jp/newsroom/2025/12/hypertension-notifications-available-today-on-apple-watch/
「労災認定 精神障害 精神障害 労災認定」に関する最新情報です。
徳島県の精神障害に関する労災認定率は全国で最も低く、わずか20.8%に留まっていることが報告されています。この結果、他の都道府県と比較して最大2.79倍の格差が生じていることが明らかになりました。一方、神奈川県では精神障害の労災認定件数が前年から倍増し、特に医療・福祉現場で自殺や未遂が目立つ状況となっています。
https://article.auone.jp/detail/1/2/5/472_5_r_20251203_1764749587271823
「リスク リスク 低下 低下」に関する最新情報です。
2型糖尿病患者が心臓や血管に良い生活習慣を維持することで、認知機能の低下を防ぐ可能性があることが、米テュレーン大学のYilin Yoshida氏の研究で報告されました。特に、認知症リスクが高い遺伝的背景を持つ患者において、この効果がより顕著であるとされています。この研究結果は、米国心臓協会の年次学術集会で発表されました。
https://www.carenet.com/news/general/hdn/61783
「悪化 鬱病 鬱病 悪化」に関する最新情報です。
この記事では、イランのエヴィーン刑務所における女性活動家の厳しい状況が描かれています。特に、ナルゲス・モハンマディが明かす非人道的な扱いについて触れられています。エヴィーン刑務所では、政治犯や思想犯が収容され、看守による暴力や性的虐待、精神的苦痛を伴う「白い拷問」が行われています。
ファティメ・モハンマディは、キリスト教に改宗したために逮捕され、独房での尋問や移動の自由を奪われることで、もともと抱えていた鬱病が悪化しました。彼女は、医療記録を知る尋問官に対しても、必要な治療を受けることができず、精神的な苦痛が増していったと語っています。このような状況は、イランにおける人権侵害の一例として、国際的な関心を集めています。
https://gendai.media/articles/-/157864
「そば処 ショーケース 昼寝」に関する最新情報です。
埼玉県さいたま市の「そば処大むら」で、ショーケースの中でお昼寝する猫・コンちゃんが話題になっています。店主のペタコンちゃんねるさんがSNSに投稿したこの姿は、訪れるお客さんの心をつかんでおり、「ぬいぐるみのようだ」との声も上がっています。冬になるとコンちゃんはショーケースで過ごすことが多く、同店にはもう一匹の猫・ペタ郎くんもおり、二匹は人懐っこい性格で人気です。お客さんたちは、癒しを求めてこの猫たちに会いに訪れるようです。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_692272a5e4b0ba57449cd0eb
「医療 糖尿病 総合」に関する最新情報です。
秋田大学の研究チームは、2型糖尿病治療薬チルゼパチドが血糖値や体重の改善に加え、食事関連の生活の質(QoL)や治療満足度を向上させる可能性があることを発表しました。この研究では、チルゼパチド治療を受けた95人の患者を対象に調査が行われ、HbA1cは7.4%から6.4%に、体重は77.2kgから70.6kgに改善されました。また、「食事療法の受益感」が有意に向上し、これは体重減少と同等に治療満足度に寄与していることが示されました。研究成果は「Diabetes Research and Clinical Practice」に掲載されています。
https://www.qlifepro.com/news/20251125/type-2-diabetes-11.html
「精神障害 103 労災認定」に関する最新情報です。
神奈川県内で2024年度に精神障害の労災認定を受けた件数が103件に達し、前年から倍増したことが報告されています。特に医療や福祉の現場では、自殺や未遂のケースが目立っており、労働環境が精神的健康に与える影響が深刻化しています。この増加は、仕事によるストレスや過労が原因とされており、労災認定の重要性が再認識されています。
https://article.auone.jp/detail/1/2/5/475_5_r_20251110_1762782128458594
「昼寝 共感 股関節」に関する最新情報です。
飼い主が昼寝をしようと布団に入ると、5匹の猫が集まってきて股関節が痛くなるというエピソードが話題になっています。この投稿には2.9万の「いいね」が集まり、他の猫飼いからも「あるある」と共感の声が寄せられています。猫たちが飼い主の股をこじ開けてくつろぐ様子が描かれ、多くの人が同じ経験を持っていることが示されています。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_690befa1e4b094b50cf8041f
「医療 糖尿病 提供」に関する最新情報です。
医療従事者向けの総合サイトでは、糖尿病に関する最新情報が提供されています。特に、筑波大学の研究により、糖尿病に関する教育が漫画を通じて行われることで、子どもたちの知識や運動習慣が向上することが示されています。1型糖尿病(T1DM)や2型糖尿病(T2DM)の増加が問題視される中、正しい知識の普及が重要です。しかし、糖尿病に対する誤解も多く、特に「怠け者の病気」といった偏見が存在します。子どもたちが健康的に生活するためには、家族や学校、周囲の理解も不可欠です。
https://www.qlifepro.com/news/20251030/diabetes-themed-cartoon.html
「検討 労災認定 最多」に関する最新情報です。
昨年度、仕事のストレスが原因で精神障害を発症し労災認定された件数が初めて1000件を超え、1055件に達しました。これは過去最多であり、労災請求全体の件数も3780件と、2010年度と比べて約3倍に増加しています。精神障害の主な要因は「対人関係」で、特に「上司とのトラブル」が6割以上を占めています。この状況を受けて、高市総理は労働時間規制の緩和を検討するよう指示し、上野厚生労働大臣は「働き方の実態やニーズを精査しつつ検討していきたい」と述べました。
https://article.auone.jp/detail/1/2/2/333_2_r_20251028_1761620893667220
「ini ini 癒さ つらく」に関する最新情報です。
吉木りさは、ワンオペ育児の辛さについて語り、「何度泣いたことか」と心情を吐露しました。その中で、INIの存在が大きな支えとなり、「本当に癒された」と感謝の気持ちを表現しています。この発言は、ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』でのものです。
https://article.auone.jp/detail/1/5/9/360_9_r_20251026_1761483025040680
「検査 リスク index」に関する最新情報です。
脳梗塞・心筋梗塞発症リスク検査「LOX-index」の累計検査数が100万件を突破しました。この検査は、血液中の酸化した超悪玉コレステロールと動脈硬化を進めるたんぱく質を測定し、将来の発症リスクを評価します。日本人の約5人に1人が心疾患や脳血管疾患で命を落とす現状を受け、予防医療の重要性が高まっています。
100万件のデータからは、リスク分類において低リスク群が64%、中リスク群が29%、中高リスク群が3%、高リスク群が4%であり、男女ともに中高リスク以上の割合は約7%とされています。これを記念して、感謝の意を込めたキャンペーンも実施され、リスク傾向の可視化やプレゼントキャンペーンが行われています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000072604.html
「医療 糖尿病 スティグマ」に関する最新情報です。
この医療総合サイトでは、医療従事者向けに最新の医療ニュースや情報、ツールを提供しています。特に注目されているのは、糖尿病に関するスティグマ(偏見)についての意識調査です。調査によると、医学生や研修医の約4割が糖尿病に対して誤ったイメージを持っており、糖尿病患者の75%がスティグマを感じているにもかかわらず、社会全体での認知度は低いという現状が明らかになりました。
スティグマは、知識不足や偏見から生じ、糖尿病患者に対して「寿命が短い」「怠惰な生活の結果」といった誤解を生むことがあります。これらの偏見は患者の社会的評価を低下させ、重要なライフイベントにおいて不当な扱いを招く可能性があります。糖尿病を持つ人々が適切な医療を受ける機会を逃すことがないよう、正しい理解を促進する活動が必要です。
この研究では、京都大学と聖マリアンナ医科大学の医学生1,369人と臨床研修医238人を対象に、糖尿病スティグマとアドボカシー活動に関する意識調査を実施し、57.3%の回答を得ました。教育段階別に分析した結果、スティグマの認識は学年が進むにつれて高まることが示されました。医療者自身がスティグマの存在を認識することが、糖尿病患者がより良い社会生活を送るための第一歩となります。
https://www.qlifepro.com/news/20251027/stigma.html
「呼吸 蘇生 人工」に関する最新情報です。
岡山大学の研究によると、コロナ禍において小児の院外心停止に対する蘇生法が変化し、人工呼吸の実施率が約12%低下したことが明らかになりました。これにより、胸骨圧迫のみの蘇生法が増加し、結果として年間約10人の子どもが本来救えた命を失っている可能性が示されています。研究は「All-Japan Utstein Registry」を用いて、コロナ流行前(2017-2019)と流行中(2020-2021)のデータを比較し、人工呼吸の減少が死亡や後遺症のリスクに関連していることを明らかにしました。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003245.000072793.html
「リスク リスク 上昇 上昇」に関する最新情報です。
新たな研究によると、聴覚障害は心不全リスクの上昇と関連していることが示されました。この研究は南方医科大学のXianhui Qin氏らによって行われ、精神的苦痛が両者の関連に影響を与える媒介因子である可能性があるとされています。研究はUKバイオバンクのデータを使用し、心不全のない164,431人を対象に実施されました。この結果は、心臓の健康問題の前兆として聴覚障害が重要であることを示唆しています。研究成果は「Heart」に掲載されました。
https://www.carenet.com/news/general/hdn/60561
「くるみん くるみん 認定 認定」に関する最新情報です。
Sky株式会社は、次世代育成支援対策推進法に基づき、厚生労働省から「プラチナくるみん認定」を取得しました。この認定は、社員の仕事と育児の両立を支援する取り組みが評価された結果です。具体的には、産前産後の休暇制度や時短勤務制度を活用し、多くの社員が育児と仕事を両立させています。今後も、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境整備を積極的に行い、子育て支援を推進していく方針です。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001028.000001552.html
「プロジェクト リトリート 整える」に関する最新情報です。
島根県の株式会社海士は、出雲地方と隠岐諸島を結ぶ新たな観光プロジェクト「『はじまりの地』で心身を整える美肌リトリート旅」を始動しました。このプロジェクトは「美肌県しまね推進事業」の一環で、地域振興と持続可能な観光モデルの構築を目指しています。出雲の「静」と隠岐の「動」をテーマにしたリトリート体験を通じて、心身のバランスを整え、地域の産業振興や文化交流を促進します。具体的には、出雲では内面を見つめる体験、隠岐では感性を磨くアクティビティを提供し、両地域の魅力を高めることを目指しています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000071239.html
「糖尿病 医療 課題」に関する最新情報です。
「糖尿病関係者調査2025」は、糖尿病治療におけるチーム医療の課題と解決策を明らかにするために実施された調査で、関西エリアの先端医療施設の協力を得て行われました。調査結果では、情報共有の不足、コミュニケーションの課題、業務負担の偏り、患者教育の不足など、チーム医療を阻害する6つの根本課題が特定され、それぞれに対する解決策が提示されています。
このホワイトペーパーは、全国の糖尿病医療従事者にとって有益な情報を提供しており、調査結果は無料でダウンロード可能です。また、協力医療機関の取り組み事例も掲載されており、他の医療従事者が参考にできる内容となっています。セカンドハート社は、患者に寄り添いながら重症化を予防することを目指しています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000135007.html
「睡眠 睡眠 障害 障害」に関する最新情報です。
日本医師会は、2025年3月5日に「健康ぷらざPlus」の最新号(Vol.6)を公開し、子どもたちの睡眠障害について特集しました。近年、睡眠障害に悩む子どもが増加していることを受けて、東京都立多摩北部医療センターの小児科部長である小保内俊雅氏が、睡眠障害の原因や症状、診断、治療法について解説しています。睡眠は子どもたちの心身の成長や健康に不可欠であり、最新号には子どもたちの睡眠状態を確認するためのチェックリストも掲載されています。保護者はこれを活用し、子どもたちの健康を支援することが求められています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000123.000128707.html