AIと言っても、看護師業務に取り入れられるものは多岐に渡ります。

看護師含め医療職は常に人手不足です。そのため、多少の資材を投じてもマンパワーに代替できるAIや医療ロボットの導入に躊躇はない業界とも言えます。

ただ、私が看護師として働いていてもどかしいと感じたのが「倫理」の問題。
患者の不利益になるような改革はなされないとしても、倫理的にグレーな判断となりAI導入が阻まれる可能性は否定できません。
この記事では、そんな看護師の倫理を理解した上で、適切なAIとの共存方法を模索していきます。
情報(データ)管理の困難さ
まず、倫理的な問題として筆頭としてあげられるのが「患者情報」の問題です。
AI成長のために必要な情報
AIは「特徴量」というものを学び取って学習していくのですが、そのためには「教師データ」となる大量の情報が必要になります。

良質なデータがあるほど、AIの学習精度と効率が高まります。つまり、どれだけたくさんの情報を提供できるかで、AI導入の進捗が変わると言っても過言ではありません。
医療業界はデータが豊富
幸いにして、医療業界は教師データが豊富な上に、ほとんどが電子化されているので導入に踏み切りさえすれば一気にAIの成長が加速します。
- 心電図・レントゲン写真などの画像データ
- お薬手帳の電子化
- 退院後の患者の通院記録
- 診療・看護記録
- 地域医療との連動記録
これらのデータを元にして、AIに活用させていきます。いわゆる機械学習(ディープラーニング)によって、人の手を離れてAIが自分で学習していくことも可能になります。
データの精度を上げるコスト
ちなみに、データがあっても、AIに読み取らせるためにはまた別のコストが必要になります。AIが学習するための前段階として、例えば画像診断の場合は画像を読み取らせるだけではなく、「これが癌の特徴だよ」と正解の印をつけていく作業があります。

例えば普遍的な「文字」認識とかだと、安い報酬で暇な人にやってもらえればいいけど、医療データの場合は「専門家」が責任を持って「正解を教える」作業が、どうしても一定数は必要になります。
つまり、医者や画像診断の専門家を雇う必要があるわけで、つまり人件費が高くつきます。
看護記録も立派な教師データ
看護記録も大きな病院ほど電子化されています。

私が働いていたところも看護記録はもちろんのこと、看護実績や温度板まで、何から何までパソコンで入力してたよ!
これらのデータはフォーマットの問題はあるにせよ、AIに読み取らせることで教師データとなりうる貴重な資料です。
患者の言動・心理を読み解く特異性
看護記録の場合は、患者の言動などの記録もあるので、状態変化の兆しのようなものを発見できる足がかりとなる可能性があります。つまり、データの変化から患者の急変の可能性を予測し、その対応方法までAIが指示・提案してくれる未来がある、可能性があります。
ベテラン看護師になれる
これまでは、ベテラン看護師の予感的なもの、経験から推測されたものを頼りに患者の状態変化を予測していたけど、これだと経験年数によって看護師の提供できるサービスに差が出てしまいます。
AIを補助的に利用することで、経験年数による差が補われて、新人看護師でもある程度はやるべきことの予測がたつようになることが期待されます。
データ利用には同意が必要
ただ、この豊富なデータを患者の同意なく利用できるのか、というのはひとつの問題。患者のデータは当然、個人情報に当たります。勝手に利用すれば罰せられるのは当然ですが、倫理的にも患者の同意なしに医療データを利用するのは問題となります。
医療データは高い
個人情報でも、医療データというのは価値が高いとされています。研究・開発に利用される場合でも悪用される場合でも、「病気」のデータは利用のしがいがあるのです。
データの持ち出しが容易になる
また、AI導入には必ず専門の外部機関に依頼することになります。ここでも大きな問題があり、守秘義務違反となることが予想されます。

丹念に個人情報につながるデータと必要なデータを切り話せればいいのですが、「どの個人情報はアウト」で「医療データならOK」とするかの線引きも曖昧です。
外部の人間を入れることで、情報漏洩リスクは劇的に高まります。
悪用のリスク
先ほども申し上げたように、医療データは高いので悪用したい人は必ず目をつけます。信用の問題にもなりますが、外部リソースを導入する場合は「漏洩すること」を前提にしなければならず、大きな課題を残している状態と言えるでしょう。
まずは法・規約整備
この医療データの利用は、法律で一律「利用できる」ようにしちゃえば話は簡単になります。

おそらく、今後は病院も、データを利用できるように通院・入院の際に患者から事前に同意を取るようになるでしょうね(なってるかも)
お金になることなので、政府は積極的に医療データを活用し始めると思いますが、さらにマイナンバーあたりと紐付けして「医療」「経済」「政治」なんかの要素と連動させることでしょう。
病院がデータを売る
データを売る、というと悪い響きがしますが、病院の経営は本当に死活問題です。本来、病院が無くなったら困る人たちが負担すべき医療費なのですが、しわ寄せは医療従事者の労働環境にまで響いており、悪循環が止まりません。

例えば、病院が持つ医療データは本来無料で共有できるべきですが、これを有料化することで病院経営の負担を減らすことができる、ということも可能かもしれません。
患者情報なので、とてもいいこととは言えませんが、将来的に医療者確保のためには賃金を上げる必要はあるし、医療の発展にもお金はどうしても必要です。

だからって患者に「お前の治療だからもっと金払え」は言えない。だけど、「医療データを活用することで貢献してくれ」と言われれば負担は少ないからOKする方もいるでしょう。
データが活用されて医療の発展につながれば社会全体には意味のあることです。発展型に、患者が同意すれば病院からメルマガのような媒体で患者に「検診のお知らせ」などの情報を提供し、そこに広告枠をつくることで収入源を増やすこともできます。
患者の安全を守れるのか
倫理綱領の基本は、「患者を守ること」です。患者の安全も守られるべきものであり、「AIの判断」や「医療デバイスの技術的な過誤」など、AI導入により懸念される問題はあります。
責任の問題
まず、「責任」の問題があります。AIはデータから最善策をアドバイスしてくれるようになります。当然、看護師含め実施者が医療行為の責任を負うことにはなりますし、法的にもそのように整備されていくことでしょう。

でも、AIの最善策を無視して事故が起きても「なんでやらなかったんだ」って怒られるし、AI指示を遵守してても「医療者としての素質を問う」ということになりそう。
倫理綱領における看護師の責任問題
倫理綱領7条には「看護者は、自己の責任と能力を的確に認識し、実施した看護について個人としての責任をもつ。」という条項があります。また、第8条においても、「看護者は、常に、個人の責任として継続学習による能力の維持・開発に努める。」ということで、自己研鑽しないと倫理的にアウトですよ、と窘められております。

結局のところ、個々人の意識の問題にはなるんだけど、AIネイティブ世代ほどこの辺りの意識は薄れてくると思います。それが予測される以上、AI導入は「危険」と考えられて導入されない可能性もあります。
医療デバイスの不備
また、患者の身体情報を正確に認識していることがAI稼働の第一条件となりますが、AIをサポートする医療デバイスが安全に使われるかどうか、なんかも一つの議題となりそうです。
例えば、身体装着型のデバイスを患者さんが装着している場合、「しっかりと身につけているか」をチェックするのは看護師の役目といえるでしょう。ただ、患者が意図的に外していた場合まで看護師に責任を問うのか、あるいはデバイス側にエラーが起きていた場合は、どこに責任がいくか、などは曖昧です。
どんな場面でもケースバイケースではありますが、「そんなのやってみないとわからないよね」と気軽に導入できるものでもないので議論ばかりが繰り返されて導入が遅れる可能性はあります。
患者の拒否権
少し話題に出しましたが、患者の信念として「AIは信用できないから利用しないでくれ」ということは大いにあり得そうです。その場合、医療者側で対応できるのか、対応できないから治療せずに患者を帰すのかは倫理的な問題と言えるでしょう。
看護者は、国籍、人種・民族、宗教、信条、年齢、性別及び性的指向、社会的地位、経済的状態、ライフスタイル、 健康問題の性質にかかわらず、対象となる人々に平等に看護を提供する。
患者個人の信念は尊重されるべきものです。しかし、AIが関与しているとする線引きが難しく、患者が納得して治療できるか深く話し合う必要は出てくるでしょう。

そもそもAIの何が嫌なのか、患者さんがどうしたら満足できるのかっていうところからしっかりと向き合わないといけないだろうね。
AI導入しないのも倫理的な問題
ちなみに、AI導入が医療倫理的に問題があるかのように書いてしまいましたが、発展し続ける技術を利用しない、というのも実は倫理的には問題があるとも言えます。

つまり、医療の発展自体は患者の役に立つものなのに、それを取り入れないことは医療的な怠慢ともいえるわけです。
看護師の負担軽減
例えば、看護師の負担を軽減することでインシデント率が変動することは知られています。看護師自身の心身の健康を保つことも重要であると倫理綱領では述べられています。
看護者は、より質の高い看護を行うために、看護者自身の心身の健康の保持増進に努める。
現時点では、どの医療機関も蔑ろにしていますが、マンパワー不足なんて言い訳です。しかるべき報酬と休暇を提示して医療者を集めれば、人手不足にはなりません。
ただ、現実問題として病院も経営ですので、利益のないことはしませんし、絞り取れるところからは搾り取って利益としていく必要があります。

だから、看護師がウダウダ言いながらも低賃金・サービス残業をよしとして働いている限りは、経営者としては御の字で状況を変える必要はない、ということになるよね。

NOといえる労働者は少ないし、酷使するほど「現状打破するバイタリティ」も削り取れるから、経営側としてはこのまま「マンパワー不足」の状態で働かせたいだろうしね。
安全な医療を提供するには体も資本
前置き(愚痴)が多くなりましたが、例えばAIを導入することで看護師の負担を減らせば医療事故が減らせる、となれば導入しないのが倫理的に問題と言えます。

なので、看護師の皆さんは現状に不満があれば「働き方改革」として無理な労働を強いられたらインシデント発生させるといいですよ。状況改善の必要性が増しますから。
医療事故を起こせは冗談ですが、声を上げないと何も変わらないし、行動しないと損をする、というのは世の常です。心しておきましょう。
言語の壁を乗り越えて平等な医療を提供する
ついでに、AI導入でわかりやすい効果として、「言語の障壁が減る」というものがあります。

AIは言語習得が容易です。AI通訳用に文法上伝えやすい「AI日本語」を使用できるとなお良いですね。
スマホなどの携帯デバイスと通訳AIは相性が良く、携帯型医療デバイスにも組み込みやすいと考えられます。

要は、看護師はスマホを持ち歩くようになるし、そのスマホには通訳アプリが入ってる、ってことね。遊んじゃいそう。
利用者の技術的な障壁が低い(誰でも簡単に使える)ので、この辺りはすぐに導入されることでしょう。

病院経営されている方は、医療英会話研修するよりもスマホ講座した方がいいよ!
AIが患者行動を変える
また、アメリカではもうすでに積極的に医療データを経済活動に反映させています。私の別サイトではスマートウォッチのレビューなんかもしているのですが、「健康データ」が商売に利用されはじめており、健康維持のための行動が今後は変わってくるかもしれません。
患者も専門家になれる
専門家になれる、は言い過ぎですが、家庭(在宅)医療の段階である程度の診断が可能になります。

つまり、自分の今ある症状をAIに調べさせて、そのまま診療できるクリニックにつないで、電子処方箋を発行してもらい近所の薬局で薬をもらう(ドローンが届けるまであり)。
家にいながら、スマホなどの通信デバイスさえあれば診察・処方までしてもらえます。大きな病院に係る必要性は薄れます。
治療の必要性は患者任せ?
これは、同時に患者自身が自分の「医療行為」に責任を持つ必要がある、ということにもなります。

AIに診断を任せて受診行動をとらない人も多くなるけど、それって自己責任だよねってこと。
スマホ経由の診断で、例えば重大な疾患を見逃して脳炎を「風邪」として診察したクリニックに関しても、「診察に必要なデータが提供されなかった」として患者(とAI)の自責を問うこともできるようになるのではないか、と考えられます。

予防線をはれば、「風邪の可能性はありますが念のために受診を」と言っておけばいいだけだしね。大概の人は、「風邪ならいいか」で受診まではしないだろうし。
裁判用のデータは残る
全ての記録が残るので、裁判系はスムーズに判決が出そうですね。
医療データで予防行動を
例えば、医療データを他のデータと組み合わせることで、「患者未満の病気予備軍」に対してアプローチをかけることもできるようになります。

看護師的に言えば、「今日は寒いから脳梗塞に注意しよう」みたいなのが、一般の人にも警告として出せるってことね。
個人情報は多岐にわたり、環境データとも連動すれば、「気温が急激に下がる」「コレステロール値が高い」「持病に心疾患」「直近の心電図」なんかが紐づけられて、「お勧めの過ごし方」なんかが提案されるわけです。

また、受診行動が取れていない場合は、市役所から直接「検診の依頼」なんかが来たり、乳がん検診のクーポンをアプリで発行できたりするわけです。
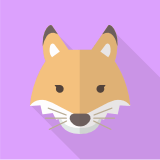
経済活動で言えば、病気リスクの高い人に「健康食品」を提案したり、治療行動に関心の低い層には売り込みやすい別の商品を広告したり、なんて活用方法があるね。
上げたらきりがありませんが、医療データが外に出て動き始めると、世の中は劇的に変化するということだけはお伝えしておきたい。
AIに踊らされないように
ここまでAIを連呼してきましたが、基本的には一つのツールでしかありません。ツール(道具)は使い手によって如何様にも変化します。

今後AIが発展してくると、AI過誤の報道が加熱したり、職場でも振り回されることが多くなると考えています。
ですが、基本的には自分の行動には責任を持ち、医療者としての職務を全うするのが看護師という仕事です。

AIを活用することで医療はさらに進歩するのは確実です。その時に、上手に使いこなすプロの看護師になることが、まずは我々の使命と言えそうです。
AIにまつわる倫理問題とその取り組み方
取り急ぎ、参考になったサイトなんかを載せておきます。
医療業界の取り組み
ネットでの広いものではありますが、2018年の段階で医師会でも勉強会しているみたいですね。医者の負担が増えるのは歓迎しないけど、将来のためには大事な話し合いですね。
看護者の倫理綱領
- 看護者は、人間の生命、人間としての尊厳及び権利を尊重する。
- 看護者は、国籍、人種・民族、宗教、信条、年齢、性別及び性的指向、社会的地位、経済的状態、ライフスタイル、 健康問題の性質にかかわらず、対象となる人々に平等に看護を提供する。
- 看護者は、対象となる人々との間に信頼関係を築き、その信頼関係に基づいて看護を提供する。
- 看護者は、人々の知る権利及び自己決定の権利を尊重し、その権利を擁護する。
- 看護者は、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に努めるとともに、これを他者と共有する場合は適切な判断のもとに行う。
- 看護者は、対象となる人々への看護が阻害されているときや危険にさらされているときは、人々を保護し安全を確保する。
- 看護者は、自己の責任と能力を的確に認識し、実施した看護について個人としての責任をもつ。
- 看護者は、常に、個人の責任として継続学習による能力の維持・開発に努める。
- 看護者は、他の看護者及び保健医療福祉関係者とともに協働して看護を提供する。
- 看護者は、より質の高い看護を行うために、看護実践、看護管理、看護教育、看護研究の 望ましい基準を設定し、実施する。
- 看護者は、研究や実践を通して、専門的知識・技術の創造と開発に努め、看護学の発展に寄与する。
- 看護者は、より質の高い看護を行うために、看護者自身の心身の健康の保持増進に努める。
- 看護者は、社会の人々の信頼を得るように、個人としての品行を常に高く維持する。
- 看護者は、人々がよりよい健康を獲得していくために、環境の問題について社会と責任を共有する。
- 看護者は、専門職組織を通じて、看護の質を高めるための制度の確立に参画し、よりよい社会づくりに貢献する。

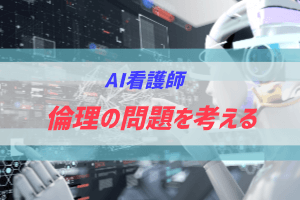
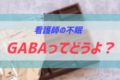
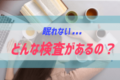
コメント
「医療 提供 サイト」に関する最新情報です。
この医療総合サイトでは、運動麻痺患者に対するロボットリハビリの最新情報が提供されています。大阪公立大学が開発した新しいデジタルトランスフォーメーション(DX)システムにより、医療者が行う手の麻痺検査データをもとに、ロボットが最適なリハビリプログラムを自動推薦できるようになりました。このシステムは、ロボットリハビリの経験がない医療者でも効果的な治療を提供できる可能性を秘めています。しかし、効果が証明されている「ReoGo-J」は2023年4月に経済的理由から取り扱いを終了しており、再販を望む声が多く上がっています。研究グループは、さらなる研究成果が企業に届き、開発や取り扱いが再開されることを期待しています。
https://www.qlifepro.com/news/20241127/reogo-j.html
「医療 勉強会 医療 未来」に関する最新情報です。
2023年10月23日(水)に開催される第82回勉強会「マイナ保険証一本化に向けて」では、厚生労働省の担当官による講演が行われます。この勉強会は「日本の医療の未来を考える会」が主催し、病院経営者や医療従事者を対象としています。参加費は医療従事者は無料、企業参加者は10,000円(税込)で、申し込みは先着順となっています。勉強会は、健康保険証が廃止され、マイナンバーカードに健康保険証の機能が統合されることに関連した内容です。また、医療情報誌『集中』は病院経営者や医師向けに医療関連の情報を提供しており、定例勉強会を通じて医療界の問題についての情報交換を行っています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000098.000096694.html
「ai 利用 医師」に関する最新情報です。
Indeed Japanが実施した「AIの業務利用に関する実態・意識調査」では、医師の約25%と看護師の7.5%がAIを業務で利用した経験があることが明らかになりました。調査対象は20歳から59歳の医療職に従事する1,000名で、AIの業務利用に対する期待感も高く、医師の約70%、看護師の50%以上が今後の利用意向を示しています。AIによる労働時間削減の希望もあり、医師は平均21.9%、看護師は23.1%の時間短縮を望んでいます。医療現場では、AIを活用することで業務効率化や診断精度の向上が期待されており、医師や看護師からは具体的なAI活用のアイデアも寄せられています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000163.000028842.html
「医療 提供 従事者」に関する最新情報です。
この医療総合サイトは、医療従事者向けに最新の医療ニュースや情報、ツールを提供しています。筑波大学などの研究によると、リモート労働者は多要素プログラムを通じて身体活動を促進している一方で、出社している労働者は身体活動が少なく座位時間が長いため、健康リスクが高いことが示されています。また、2022年1月から3月に実施された多要素身体活動促進プログラムのパイロットRCTでは、勤務日中の中高強度の身体活動時間が有意に増加したことが報告されています。今後は、介入方法や研究デザインの再検討が求められています。
https://www.qlifepro.com/news/20240925/remote-workers.html
「がん がん リスク リスク」に関する最新情報です。
生殖補助医療(体外受精など)によって生まれる子供の数は増加しており、2021年には日本で約7万人に達しました。このような医療技術は、エピジェネティックな障害や先天奇形のリスクを伴う可能性があるため、小児がんのリスク因子として懸念されています。小児がんは小児の主要な死因の一つであり、フランスの研究者たちは生殖補助医療後に出生した子供におけるがんリスクについての調査を行っています。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/59230
「医療 提供 サイト」に関する最新情報です。
この医療総合サイトは、医療従事者向けに最新の医療ニュースや情報、ツールを提供しています。最近のニュースでは、生活保護受給者に関する新しい方針が取り上げられており、医療上の必要性が認められない場合、嗜好に基づいて長期収載品の処方を希望することはできず、後発品の提供が可能な場合には、それを処方することが求められています。この情報は、医療機関や保険薬局における調剤の方針に影響を与える重要な内容です。
https://www.qlifepro.com/news/20240826/mhlw-171.html
「医療 提供 サイト」に関する最新情報です。
医療従事者向けの総合サイトでは、最新の医療ニュースや情報、ツールを提供しています。最近のトピックとして、厚生労働省が生活保護受給者に関する指針を示しました。医療上の必要性が認められない場合、患者が嗜好に基づいて長期収載品の処方を希望しても、医療機関や保険薬局は後発品を提供することが求められ、長期収載品は医療扶助や保険給付の対象外となることが説明されています。
https://www.qlifepro.com/news/20240826/mhlw-171.html
「要件 改正 専門家」に関する最新情報です。
自民・公明・立憲民主の各党が、トランスジェンダーが戸籍上の性別を変更する際の「特例法」の改正に関する議論を進めている。現在の手術要件を見直す代わりに、新たな要件を設ける案が浮上しており、専門家からはこの改正に対する懸念の声が上がっている。
http://www.asahi.com/articles/ASS882BZVS88UTIL01GM.html?ref=rss
「遺族 被害者 裁判」に関する最新情報です。
京都アニメーション放火殺人事件で亡くなった渡邊美希子さんの遺族が、裁判において被害者の実名の公表を求める中で、被害者や遺族の心のケアや差別について問題提起している。裁判に参加するために遺族が家を借りたり休職したりするなど、困難な状況も明らかになっている。裁判のあり方や被害者の実名の扱いについて議論が続いており、社会全体での理解と配慮が求められていることが示唆されている。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_668fbadee4b0fb744167116c
「ai 医療 変える」に関する最新情報です。
孫正義が描くAI時代の医療人工超知能「ASI」は、医療データとAIを組み合わせて日本の医療を変革する可能性を持つ。遺伝子検査や電子カルテのデータをAIで解析し、患者ごとに最適な治療を提案することで、がん治療などに役立つとされる。孫氏は、人間の知能を超える「ASI」の実現に強く訴えており、AIが医療分野に革新をもたらす下地が整っていると説明している。
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2407/13/news059.html
「医療 提供 サイト」に関する最新情報です。
医療従事者向けの医療総合サイトが、新規要介護認定者の病気パターン分類や介護度悪化との関連を調査する研究について報告しています。研究では、高齢者が新規要介護認定される際の複数の疾患の組み合わせや予後について分析し、クラスター分析で6つの臨床サブタイプを同定しました。各サブタイプの特徴や死亡や介護度悪化との関連性も明らかになりました。今後は他の地域でも同様の解析が必要であり、日本での結果が普遍的かどうかも検討される必要があります。
https://www.qlifepro.com/news/20240710/requiring-long-term-care.html
「ためこま コレステロール コレステロール ためこま」に関する最新情報です。
医師が考案した「脳梗塞の時限爆弾」を解除するスープは、中性脂肪や悪玉コレステロールの蓄積を防ぎ、深刻な事態を引き起こす「悪魔のあぶら」と呼ばれる物質を防ぐ効果がある。
https://toyokeizai.net/articles/-/769812?utm_source=rss&utm_medium=http&utm_campaign=link_back
「健康 関心 健康食品」に関する最新情報です。
2024年5月に行われた高齢者向けの健康に関するアンケート調査では、参加者の4人に1人が毎月1万円以上の健康消費に関心があり、健康食品やグッズに興味を持っている人は4人に3人に上ることが分かった。特に女性や70歳未満の参加者に関心が高く、男性や80歳以上の参加者は関心が薄れる傾向が見られた。また、健康にかける毎月の金額は1万円以上を消費している人が約25%いることも明らかになった。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000140756.html
「医療 提供 サイト」に関する最新情報です。
日本の生殖補助医療において、男性の同意が問題となる裁判例が存在し、男性の同意が争いになる場面は精子提供時、凍結胚移植時、精子・配偶子廃棄時の3つに分類されることがわかった。男性の権利が侵害される背景には、法整備の欠如や男女の役割分担が影響している可能性が指摘されており、男性の同意が重要であることが強調されている。
https://www.qlifepro.com/news/20240620/reproductive-rights.html
「198 198 医療機関 中医協」に関する最新情報です。
第198回の調査によると、医療機関の8割以上が地域包括医療病棟に転換しなかったことが明らかになった。この問題の原因について中医協が調査を行うことが決定された。また、全国で心臓移植手術の見送りが16件発生しており、その実態調査も行われることが報じられた。
https://www.carenet.com/hihyomon/198.html
「医療 ツール 提供」に関する最新情報です。
東京理科大学は、医薬品の品質向上に向けた取り組みとして、品質文化醸成度評価ツールを開発しました。このツールは従業員の成長や働きがい、経営陣のコミットメント、改善活動などのカテゴリーに分けて評価し、製薬企業の品質文化の醸成度を測ることができます。この評価ツールは日本製薬団体連合会に無償提供され、製薬企業に役立てられることが期待されています。
https://www.qlifepro.com/news/20240617/tus.html
「提供 医療 サイト」に関する最新情報です。
岡山大学などの研究によると、ECMO使用ドナーの臓器提供では、肺を除いてレシピエントの生着率に影響がないことが示された。臓器提供に関しては、ECPR実施臓器の生着率が肺以外では同等であることが報告されている。臓器提供については、医療従事者だけでなく一般の人々にも正しい情報提供が必要であり、患者や家族が臓器提供を希望する場合には適切な環境と体制整備が重要であると述べられている。
https://www.qlifepro.com/news/20240607/ecmo-ecpr.html
「医療費 心配 医療費 現実」に関する最新情報です。
多くの人が心配する「老後の医療費」は実際にはそこまで大きくないという現実が示されています。定年後の家計支出の大きな変化は「非消費支出」に現れ、50代後半で月14.2万円必要となるが、60代前半で8.8万円、60代後半で3.7万円まで急激に減少することが分かっています。定年後の労働収入が限られているため、就業世帯でも非消費支出は大幅に減少する傾向にあります。
https://gendai.media/articles/-/129799
「事件 医大 裁判」に関する最新情報です。
第211回の記事では、東京女子医大の不正、甲南医療センターの研修医自殺事件、東京医科大元理事長の汚職など、医療業界の注目事件について新たな展開が報じられています。女子医大は第三者委員会で調査を開始し、甲南医療センターの病院側は民事裁判で争う姿勢を見せています。また、東京医大入試裁判では贈賄側の控訴が棄却されたと報じられています。
https://www.carenet.com/hihyowed/211.html
「医療 提供 サイト」に関する最新情報です。
日本の医療総合サイトによると、日本初の母体を介した脊髄髄膜瘤の胎児手術が成功し、24年4月までに計6件の手術が実施された。この手術により、下肢運動機能の改善や神経障害の軽減が可能とされており、従来の治療法よりも効果が期待されている。
https://www.qlifepro.com/news/20240422/fetal-treatment.html
「医療 提供 サイト」に関する最新情報です。
医療従事者向けの医療総合サイトが、対人関係が苦手な人向けの「感情認知トレーニングVR」を提供開始。新しいトレーニングプログラム「FACEDUO」も開発され、精神疾患やASDなどの発達特性を持つ人向けに提供される。このプログラムでは、人間の6つの基本感情を楽しみながら1人で繰り返し学習可能であり、精神疾患当事者の社会復帰に貢献することが期待されている。学校や企業への導入も目指されている。
https://www.qlifepro.com/news/20240408/faceduo.html
「医療 提供 サイト」に関する最新情報です。
阪大などの研究チームがALSの新たな病態機序を解明し、RGMaが関与することを発表。ALSにおける異常タンパク質の細胞間伝播を抑制する治療法はまだ開発されていない。RGMaはALSの呼吸状態と相関し、抗RGMa抗体はALSマウスの寿命を延ばし症状を軽減することが示された。神経細胞の細胞骨格動態を変化させ、バリア機能を低下させるRGMaは病態機序に関与し、バイオマーカーや治療標的として有望であることが示唆されている。
https://www.qlifepro.com/news/20240404/rgma-als.html
「負担 医療費 改革」に関する最新情報です。
維新が提案した医療制度改革案は、高齢者にも医療費負担を3割にするという内容であるが、社会保険料負担の重さを感じる中で、この案には不足があり、医療費の抑制や財源確保の重要性が指摘されている。現行の政策議論では、改革の内容よりも、いつ、どの程度実施するかが焦点となっており、簡単な解決策はないとされている。医療費の削減や社会保険料の引き下げは複雑な問題であり、増税や財源確保が必要とされている。維新の案にはキャッチアップが不十分との指摘もあり、医療制度改革にはさらなる検討と議論が必要とされている。
https://gendai.media/articles/-/125786
「医療 負担 ai」に関する最新情報です。
医療現場の負担を減らし、新たな治療法の開発を支援するために、生成AIを活用した共同研究が行われている。患者と会話して支援するシステムの開発や、詳細な診療情報を集めたデータベース作りが重要視されており、医療スタッフの負担軽減に向けた取り組みが進められている。
http://www.asahi.com/articles/ASS366D7NS36PLBJ002.html?ref=rss
「株主 筆頭 筆頭 株主」に関する最新情報です。
2024年3月4日、Shinwa Wise Holdings 株式会社は、代表取締役社長である倉田陽一郎が筆頭株主となることを発表しました。倉田陽一郎は1,100,000株を取得し、総株主の議決権の14.78%を有する筆頭株主となりました。倉田陽一郎は東京大学卒業後、金融業界やアートオークションでの経験を持つ実績豊富な人物です。今後もお客様や株主の期待を超える価値を提供することに尽力するとしています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000133.000082831.html
「医療 提供 ツール」に関する最新情報です。
医療従事者向けの総合サイトでは、ADHDの診断や治療に関する最新情報が提供されています。研究によると、ADHDやASDの診断を受けた6~17歳の子どもとその養育者を対象に、ADHDの評価ツールである「ADHD-RS-IV」を使用したオンライン診療が行われ、対面評価と高い一致率が示されました。このオンライン診療システムは株式会社MICINが提供する「curon(クロン)」を使用しています。ADHDの診断や治療においてオンライン診療が有用である可能性が示唆されています。
https://www.qlifepro.com/news/20240228/telepsychiatry-adhd.html
「がん がん 患者 患者」に関する最新情報です。
医師ががん患者になった経験から、科学的根拠のない情報に惑わされないための頼れる情報源が重要であることがわかった。医師自身が患者になった時、自分の頭の中は真っ白で何も思いつかなかった。特に診断された当日は不安に支配され、「なんで自分が」という気持ちになった。以前に患者に話していたことが自分に降りかかるなんて思ってもいなかった。
https://toyokeizai.net/articles/-/733841?utm_source=rss&utm_medium=http&utm_campaign=link_back
「医療 提供 サイト」に関する最新情報です。
医療従事者向けの医療総合サイトが、最新の医療ニュースや情報、ツールを提供しています。最新の研究によると、温泉入浴は腸内細菌叢に影響を与えることが実証されました。泉質によって影響が異なり、炭酸水素塩泉ではビフィズス菌が増加し、単純泉や硫黄泉では複数の菌が増加することがわかりました。温泉療法や健康促進プログラムでは、より個別化されたアプローチが可能になります。このサイトでは、同じカテゴリーの記事も提供されています。
https://www.qlifepro.com/news/20240214/b-bifidum.html
「英会話 バイリンガール バイリンガール 英会話」に関する最新情報です。
バイリンガール英会話のおさるさんとpecoちゃんがオンライン英語コーチングのENGLEADを受講し、コラボ動画が公開されました。おさるさんは過去にもENGLEADを受講しており、今回は2度目の受講でさらなる英語スキル向上を目指しています。一方、pecoちゃんは初めてのオンライン英語コーチングであり、動画で英語学習に対する期待や不安、学習を決意したきっかけなどを紹介しています。バイリンガール英会話のチャンネルでは、おさるさんの受講経験や実際の感想、pecoちゃんの英語学習の悩みなどが紹介されています。pecoちゃんのチャンネルでは、ENGLEADでの英語学習のきっかけや無料カウンセリングについても紹介されています。今回の動画を皮切りに、ENGLEADの受講や英語学習に取り組む様子や学習結果が複数の動画で公開される予定です。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000059434.html
「英会話 バイリンガール バイリンガール 英会話」に関する最新情報です。
「バイリンガール英会話 | Bilingirl Chika」のおさるさんとpecoちゃんがオンライン英語コーチングのENGLEAD(イングリード)を受講開始し、コラボ動画が公開されました。おさるさんは2度目の受講で、pecoちゃんは初めての受講です。動画では、おさるさんの受講経験やpecoちゃんの学習意欲などが紹介されています。ENGLEADの受講をきっかけに、おさるさんとpecoちゃんは本気で英語学習に取り組み、学習結果を複数本の動画で公開する予定です。また、pecoちゃんが受けた英語力診断と学習方法アドバイスの付いた無料カウンセリングも予約できます。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000059434.html
「ckd ckd 患者 医療費」に関する最新情報です。
広島大学の研究グループが、慢性腎臓病(CKD)の医療費負担がどの程度増加するかを調査しました。彼らは日本全国の健診データと医療費請求データを使用し、健診で早期のCKDを発見することと関連して医療費の増加の程度を分析しました。CKD患者の年間医療費の増加についての具体的な所見はまだ知られていませんでしたが、この研究によりその程度が明らかになる可能性があります。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/57939
「医療 提供 サイト」に関する最新情報です。
医療総合サイトは、医療従事者向けに最新の医療ニュースや情報、ツールを提供しています。最新の研究によると、健診後早期の受療により、ハイリスクの循環器疾患入院などが低減する可能性があることが示されました。重症化ハイリスク者の早期受療が重要であり、脳卒中や心不全の入院リスクが顕著に低下することが関連付けられています。この研究は、匿名化された健診・レセプトデータを分析して行われ、外部の有識者にも提供されています。
https://www.qlifepro.com/news/20240131/medical-check-up.html
「医療 提供 医療 従事者」に関する最新情報です。
この医療総合サイトは、医療従事者向けに最新の医療ニュースや情報、ツールを提供しています。最新のニュースの一つは、大学病院改革に関する指針案です。この案は、大学病院の収入が増える一方で支出も増えているため、医療提供体制の拡大に対応するための改革プランを策定することを促しています。また、このサイトは医療従事者向けのコンテンツであり、利用には医療者認証システム「QLM ID」でのログインが必要です。利用は無料で、統一IDで全ての医療者向けコンテンツにアクセスすることができます。
https://www.qlifepro.com/news/20240131/mext-13.html
「気温 変化 気温 変化」に関する最新情報です。
24日の地域別の気温変化と最適な服装についての情報が提供されています。北日本では風が強く吹くため、風を通しにくい上着が効果的です。関東では真冬用の防寒具や手袋が必要です。近畿、中国、四国地方ではさらに寒くなるため、最大限の防寒対策が必要です。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65af779ee4b0d65b024dbd14
「尾身 コロナ 専門家」に関する最新情報です。
「君は歴史の審判に耐えられるのか?」というタイトルの記事は、コロナ禍で尾身茂によって提起された重要な問いについて取り上げています。記事は、コロナ専門家がなぜ消されたのかという疑問を探求しています。
記事は、2024年1月19日に起きた出来事を基にしています。尾身茂はコロナ専門家であり、厚生労働省のコロナ緊急対策室に所属していました。記事では、尾身茂がパンデミックの初期から不眠不休で取り組んでいたことや、彼がコロナ専門家としての知識と経験を活かしていたことが紹介されています。
また、記事では尾身茂によって提起された問いについても触れられています。彼はコロナ専門家としての立場から、パンデミックとの闘いにおいて歴史の審判に耐えられるかという究極の問いを投げかけています。
記事はさらに、コロナ専門家がなぜ消されたのかという疑問についても探求しています。専門家が消されたという事実は、コロナ禍における情報の操作や隠蔽が行われている可能性を示唆しています。
この記事は、コロナ禍における尾身茂とコロナ専門家の役割についての興味深い洞察を提供しています。彼らが直面する未
https://gendai.media/articles/-/123117
「医療 提供 サイト」に関する最新情報です。
この医療総合サイトは、医療従事者向けに最新の医療ニュースやさまざまな情報やツールを提供しています。最新の記事では、筑波大学の研究によると、ノンアルコール飲料は男性の飲酒量の低減に、女性の飲酒頻度の低減につながることがわかりました。この研究では、飲酒制限はなく、4週に1回、計3回のノンアルコール飲料が無料で提供されました。男性は飲酒日あたりの飲酒量が減少し、女性は飲酒頻度が減少しました。性差はあるものの、ノンアルコール飲料は男女を問わず飲酒量の低減につながることが示されました。このサイトでは、医療に関連する他の記事も提供されています。
https://www.qlifepro.com/news/20240119/non-alcoholic-2.html
「情報 リスク 経済」に関する最新情報です。
世界経済フォーラムの報告書によると、「誤報・偽情報」が短期的な最大のリスクとされています。報告書は、情報の改ざんや社会的不安と結びつくことで、誤報や偽情報がリスクの中心となる可能性を指摘しています。特に、アメリカの経済選挙を踏まえて、デジタルリテラシーキャンペーンを通じて個人や国家のレジリエンスを強化する必要があるとされています。報告書は、企業や組織が情報の仲介者としての役割を果たす戦略的な誤算や脅威に対応するために、リスクの見通しを根底から覆す必要があるとも述べています。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/wtf_jp_659f87cfe4b0712b12c39938
「情報 リスク 経済」に関する最新情報です。
世界経済フォーラムの報告書によると、「誤報・偽情報」は短期的な最大のリスクとされています。報告書は、情報の改ざんや社会的不安と結びついた誤報や偽情報の流布が、個人や国家のレジリエンスや脅威への適応能力を弱める可能性があると指摘しています。報告書はまた、デジタル・リテラシー・キャンペーンを通じて個人や国家のレジリエンスを強化する必要性を強調しています。世界経済フォーラムは、1400人以上の専門家や政策立案者、業界リーダーなどが参加し、リスクに関する調査結果を作成しています。報告書は、世界の不安定な秩序や異常気象の影響など、経済の確実性に関わるリスクも取り上げており、指導者たちは短期的な危機に対処するだけでなく、持続可能な未来のための基盤を築くために団結する必要があると述べています。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/wtf_jp_659f87cfe4b0712b12c39938
「医療 提供 サイト」に関する最新情報です。
この医療総合サイトは、医療従事者向けに最新の医療ニュースやさまざまな情報やツールを提供しています。最新の記事では、在宅非がん高齢者の苦痛症状が十分に緩和されていないことが報告されています。筑波大学の研究によると、訪問診療を受けている65歳以上の非がん患者の中で、体の動かしにくさやだるさに関する困難が1年間変わらず続いていることが明らかになりました。この結果から、在宅非がん高齢者へのケアや支援の改善が必要であることが示唆されています。このサイトでは、同じカテゴリーの記事も提供されています。
https://www.qlifepro.com/news/20240110/elderly-non-cancer-patients-at-home.html
「攻撃 医療機関 脆弱性」に関する最新情報です。
近年、医療機関がサイバー攻撃の標的となっており、取引先の脆弱性を突かれています。医療機関では電子カルテシステムや会計システムなどが攻撃の対象となり、データの暗号化や業務の支障をきたす可能性があります。具体的な被害事例として、大阪府の病院では10億円を超える被害が発生し、患者の命に危機が生じる事態となりました。また、他のケースでは、医療機関の取引先の脆弱性を突いて侵入し、マルウェアの感染や患者情報の流出が起きています。医療機関はセキュリティ対策を講じることが重要であり、セキュリティソフトの導入や脆弱性対策の徹底、バックアップの取得と管理などが必要です。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000076503.html
「同意 shelly shelly 語る」に関する最新情報です。
タレントのSHELLYさんが、恋人や夫婦間でも性的同意が重要であることを語っています。SHELLYさんは、内閣府とのコラボレーションで、同意の重要性について啓発活動を行っています。同意は、相手の気持ちを確認し合うことであり、断ることもできる権利です。SHELLYさんは自身の体験談を交えながら、同意のポイントについて解説しています。また、2023年には刑法改正により、不同意わいせつ罪が導入される予定です。SHELLYさんは、同意のイメージをお菓子に例えて説明し、パートナーとの関係性やコミュニケーションの重要性を強調しています。同意を確認するためのポイントとして、言葉で伝えることや状況を確認することが挙げられています。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/sexconsent-shelly-video_jp_65790d98e4b0fca7ad2288aa
「医療 提供 サイト」に関する最新情報です。
この医療総合サイトは、医療従事者向けに最新の医療ニュースや様々な情報、ツールを提供しています。最新のニュースの一つは、看護師長のリーダーシップ測定尺度であるILSの日本語版の開発についてです。この尺度の開発により、エビデンスに基づいた実践(EBP)の推進に期待が寄せられています。しかし、日本の看護分野ではEBPの普及が遅れているという課題もあります。さらに、現場でのEBPの実装においては、管理者の戦略的なリーダーシップ評価の尺度の開発と検証も行われています。日本語版ILSは、自己評価用と他社評価用の両方で、オリジナル版と同じ構造を持っていることが確認されています。また、看護学の学習や研究経験があるほど、ILSの得点が高くなる傾向があります。さらに、EBPの学習や取り組み経験がある管理者も高い得点を示しています。ただし、スタッフの回答得点には、管理者との関係性などが影響する可能性があるため、さらなる検証が必要です。このサイトでは、他にも医療に関連する記事が提供されています。
https://www.qlifepro.com/news/20231218/implementation-leadership-scale.html
「医療 提供 サイト」に関する最新情報です。
この医療総合サイトは、医療従事者向けに最新の医療ニュースや様々な情報、ツールを提供しています。最新の介護給付費分科会の記事では、老健施設の薬剤調整評価についての情報が提供されています。また、同じカテゴリーの記事では、行政や経営に関する情報が提供されています。このサイトは、医療従事者が必要とする情報やツールを提供するための総合的なリソースとなっています。
https://www.qlifepro.com/news/20231213/mhlw-111.html
「判決 勝訴 裁判」に関する最新情報です。
「最低最悪の判決」から「最高の判決」にいのちのとりで裁判、またまた勝訴!
名古屋高裁で行われた生活保護基準額の引き下げに関する裁判で、原告団が勝訴しました。この裁判は、2013年に第二次安倍政権が生活保護基準額の引き下げを行ったことに対して、全国29都道府県の1000人以上の生活保護利用者が訴えを起こしたものです。この裁判は通称「いのちのとり裁判」と呼ばれ、名古屋高裁の判決が最低最悪とされていましたが、今回の勝訴によって最高の判決となりました。
12月1日には、名古屋で原告団と弁護団が集結し、勝訴を祝う緊急集会が開催されました。この裁判の勝訴は画期的なものであり、生活が苦しい人々にとっては大きな救いとなります。また、神奈川でも同様の裁判が行われており、11月には神奈川の原告団の一人が勝訴しました。この原告団には、薬害B型肝炎の被害者も含まれています。
裁判で勝訴した原告団には、10年前から裁判に参加してきた人々やがんを患っている人々もいます。彼らは生活保護の引き下げに
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65700054e4b01a04ad910ac9
「予防 予防 医療 医療」に関する最新情報です。
予防医療普及協会は、法人会員制度の創設を記念してイベントを開催し、100名以上の法人関係者が参加しました。この制度は、企業、医療法人、自治体などが連携して予防医療を推進するためのものであり、今日から会員の募集が開始されました。イベントでは、講演や交流会が行われ、予防医療に関する最新の事例や取り組みが紹介されました。また、法人会員には、病院やクリニック、薬局などが参加し、専門家相談会や健康に関する商品やサービスについての相談もできるようになっています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000023269.html
「医療 提供 サイト」に関する最新情報です。
この医療総合サイトは、医療従事者向けに最新の医療ニュースやさまざまな情報・ツールを提供しています。最新の記事では、再生医療法に基づく自由診療の有害事象が適切に報告されていない可能性があることが指摘されています。また、再生医療法の下で「医療の安全性の確保」が本当に果たされているのかについても議論されています。研究に比べて治療としての投与が桁違いに多い一方、有害事象の報告件数は治療の方が少ないことが示されています。再生医療等の製品では、3〜4回の投与に対して1回の報告があることも報告されています。さらに、2つの法制度における有害事象報告の頻度の差が重要な結果として取り上げられています。このサイトでは、同じカテゴリーの記事も提供されています。
https://www.qlifepro.com/news/20231124/ae-regenerative-medicine.html
「いつも いつも 椅子 なれる」に関する最新情報です。
ドクターエアは、いつもの椅子で心地よくなれるシート型マッサージャーを発売しました。このマッサージャーは、河原塚英信氏が開発した3Dマッサージ機能を搭載しており、首や腰など約70cmの範囲で筋肉をもみほぐすことができます。さらに、首のマッサージには4種類のマッサージモードがあります。マッサージの強さや角度も調節可能で、身長の差にも対応しています。マッサージの種類や動作は自由にカスタマイズでき、マニュアルコースも備えています。このシート型マッサージャーは、ドリームファクトリーから10月26日に発売され、価格は49,830円です。
https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/1542202.html
「医療 提供 サイト」に関する最新情報です。
この医療総合サイトは、医療従事者向けに最新の医療ニュースや様々な情報・ツールを提供しています。最新のニュースや情報を通じて、医療従事者は最新のトレンドや研究結果にアクセスすることができます。また、さまざまなツールも提供されており、医療従事者の業務をサポートするための便利な機能が提供されています。
最新のニュースの一つとして、「脳死判定」に関する新たなガイドラインが米国神経学会など4つの学会によって作成されました。このガイドラインは、医療団体によって公表され、脳死判定に関する基準や手順が明確化されています。これにより、医療従事者はより正確な脳死判定を行うことができます。
また、このサイトでは同じカテゴリーの記事が海外からも提供されています。これにより、医療従事者は国内だけでなく、海外の最新の医療情報にもアクセスすることができます。国際的な視点からの情報収集が可能となり、医療従事者の知識やスキルの向上に役立ちます。
この医療総合サイトは、医療従事者が最新の医療ニュースや情報にアクセスし、さまざまなツールを利用して業務を効率化するための貴重なリソース
https://www.qlifepro.com/news/20231023/brain-death-guideline.html
「医療 提供 サイト」に関する最新情報です。
この医療総合サイトは、医療従事者向けに最新の医療ニュースや様々な情報、ツールを提供しています。筑波大学の研究によると、ノンアルコール飲料を摂取することで飲酒量が減少することが実証されました。しかし、ノンアルコール飲料が飲酒量にどのような影響を与えるのかはまだ解明されていません。この研究では、月に1回以下の飲酒習慣を持つ男女123人を対象に調査が行われました。介入群では、ノンアルコール飲料がアルコール飲料に置き換わることで飲酒量が減少した可能性があります。ただし、20歳未満やアルコール依存症の影響を考慮しつつ、効果を追加検証する予定です。この記事は、医療カテゴリーの他の記事と一緒に掲載されています。
https://www.qlifepro.com/news/20231010/non-alcoholic.html
「医療機関 サービス 対象」に関する最新情報です。
ソニー生命保険株式会社は、先進医療給付金の医療機関あて直接支払サービスの対象医療機関を拡大することを発表しました。このサービスは、高額な先進医療の経済負担を軽減し、安心して治療を受けることができるものです。これまで24の医療機関が対象となっていましたが、今後さらに医療機関の追加や変更が行われる可能性があります。詳細な情報は公式ウェブサイトで確認できます。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000287.000003638.html